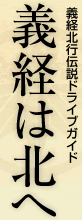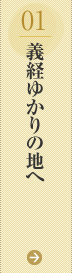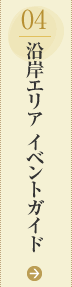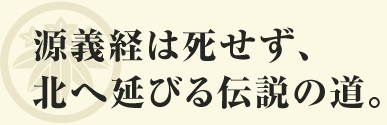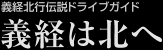われは故山に帰りたし―1227年、蒙古のトルメゲイ城で成吉思汗(ジンギスカン)は謎の言葉を残し息を引き取った。蒙古生まれであるはずの成吉思汗が、帰りたいと望んだ「故山」とはどこなのか…。今なお囁かれるのは、成吉思汗と源義経が同一人物だったとする「義経北行説」。これを現代の名探偵が解明していくのが、高木彬光(たかぎ あきみつ)の歴史推理小説「成吉思汗の秘密」だ。歴史書から導き出される大胆な考察は、800年前の伝説を魅力的に描き出している。 日本の正史「吾妻鏡」によると、源義経は文治5年(1189)、藤原泰衡軍の攻撃により平泉の持仏堂で妻や娘とともに自害し果てたことになっている。そして成吉思汗が歴史の表舞台に登場するのは、この戦いからおよそ5年後の1193年~1194年のこと。兄頼朝の追討を逃れて北に向かった義経が、北海道を経て大陸に渡り成吉思汗と名乗ったと考えるに、不自然な年月ではない。しかも成吉思汗は即位のとき、九旒の白旗を興安嶺(こうあんれい)上にひるがえしたと歴史書「蒙古史」は伝えている。白旗は源氏の旗印であり、九旒は義経の別称である九郎判官に通じる。ここに「我こそは九郎判官義経である」という、隠されたメッセージを読み取ることはできないだろうか。
それでは義経は、どういう経路をたどって北海道まで行き着いたのか。館のあった衣川を出立し、北上川を渡って対岸の岩谷堂、大股、世田米、宮古、そして八戸から津軽半島の三厩へと、足どりを明確に伝える史跡がルート上に残されている。中でも宮古周辺には、判官館、法冠神社、判官宿、弁慶腰掛岩、黒森山に判官稲荷とゆかりの地名がとても多い。しかも黒森山の古文書「判官稲荷神社縁起」には驚くべきことが書かれている。
 ―ついに秀衡錦嚢(きんのう)の遺書を開きてこれを読み、蝦夷地への道を得たり。ここにおいて君臣感泣し、意を決して中夜、館を去り、逃れて宮古に来たり…。
―ついに秀衡錦嚢(きんのう)の遺書を開きてこれを読み、蝦夷地への道を得たり。ここにおいて君臣感泣し、意を決して中夜、館を去り、逃れて宮古に来たり…。
義経の身を案じた藤原秀衡が、蝦夷地(北海道)への道を遺書に記していた。それは藤原氏の栄華を支えた黄金の産出地が、東北を越え北海道まで及んでいたからではなかったか。だとすれば義経の北走も、頼朝から逃れるための絶望的な敗走ではなく、再起のためのチャンスと軍資金を求めての旅だったとも想像できる。しかも海を越えたシベリア地方は、さらに膨大な黄金が眠る“黄金郷”だったのである。
まだ見ぬ未開の大地へ、胸躍らせて歩を進める義経一行。北への道しるべには、夢とロマンが満ち満ちている。